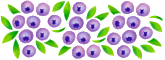
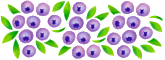 |
| 一つ前へ|平成15年度関西支部例会 特別講演Ⅰ 抄録|平成15年度寛大支部例会 特別講演Ⅱ 抄録|平成15年度関西支部例会 教育講演 抄録|シンポジウム1 抄録|シンポジウム2 抄録|シンポジウム3 抄録|平成16年度日本東洋医学会和歌山県部会講演会のお知らせ |
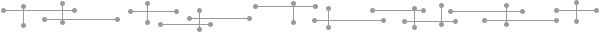 |
|
特別講演Ⅰ
千葉古方による附子剤の使い方 富山医科薬科大学副学長・病院長 寺澤捷年 いわゆる千葉古方は奥田謙蔵門下によって形成された一学派であり,和田正系,藤平健,小倉重成,伊藤清夫などの活躍は夙に知られている。 この千葉古方の人々が他の学派の方々に比して附子剤を多用したことが今回,この演題を指定された一つの理由であろうと考えている。 私の知る処では藤平の「併病論」,あるいは小倉の「潜証論」が附子剤活用の大きな背景となっている。しかし,この論旨は実は歴史的には正しくない。なぜなら藤平,小倉らは「証に随って」薬方を運用するという地道な経験の中で,附子剤の証が潜んでいたり,併存したりすることを発見し,これを論理的にまとめ上げたのであって,「併病論」や「潜証論」が先にあったのではないからである。 小倉の業績で特筆すべきことは,附子剤の中でも烏頭の利用を再発掘し,道を切り拓いてくれたことである。これにも歴史があり,四逆湯,茯苓四逆湯では解決できない症例を多数経験し,その打開策として烏頭桂枝湯,烏頭湯,そして赤丸料へと展開して行った経緯がある。 そして赤丸料の追試については伊藤隆の業績があり,通脈四逆湯については三潴忠道の業績へと連なっている。 ここでは附子剤(烏頭剤)についての臨床経験を示すと共に,潜証を見つけ出す有力な負荷試験としての「電気温鍼法」について述べる。 (本文中 敬称略) |
 |
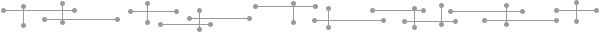 |
|